こんにちは、ももたろ。です。
2月と言えば節分。幼稚園や保育園では豆まきの行事があったりして。
子どもたちは先生扮した鬼たちに豆を投げつけて喜ぶ。
そんな楽しい行事ですね(*’▽’)笑
節分=豆まきという式が子どもたちのなかで出来あがっています。
でも、どうして節分に豆をまくかを知っている子どもは少ないのではないでしょうか。
節分に豆まきをするのはなぜでしょう?
節分とはこんな日のこと
『2月3日、節分の日に豆まきをする』
こんなふうに思い込んでいる子どもも大人もいっぱいいると思います。
↑わたしもそう思い込んでいた大人のひとりですが(;’∀’)
でも本来、『節分』とはその文字で表わされた通り、『季節』を『分ける』日のことです。
日本にはご存知の通り4つの季節がありますね。春・夏・秋・冬。
節分とは、その季節の変わり目である『立春・立夏・立秋・立冬の前日』のことをいい、もともとは年に4回あります。
しかし春から新年が始まった昔の暦では、立春前日の節分は現在の大晦日に相当する大事な1日として特に重要視されました。
こうして時代の移り変わりと共に立春の前日が節分として残っていったようです。
節分って何月何日?2019年の節分は?
節分は2月3日と思われている方が大勢いますが、その年によって変わります。
立春の前日が節分となるので、立春の日付が前後すれば節分の日も変わります。
『節分は、大体2月3日あたり』というのが正しいです。
はい。
2019年の節分は2月3日です(*’▽’)
すると、立春は2月4日、ということになりますね。
立春は太陽の動きを元に計算して日付を決めているので、たまに2月3日になったりもするようです。
節分に行われる行事~豆まき
昔は季節の変わり目、特に年の変わり目には邪気が入りやすいと考えられており、節分には様々な邪気を祓う行事が各地で行われていました。
子どもたちの大好きなこの『豆まき』がそんな行事のひとつですね(´-`*)
豆まきの由来
新しい季節が来る前に邪気を祓って幸福を呼び込むため、追儺(ついな)という宮中行事が行われてきました。
この追儺(ついな)はもともと古代中国で行われていた邪気祓いの行事で、奈良時代に日本に伝わり、平安時代に宮中行事として取り入れられたようです。
その中の行事のひとつ『豆打ち』が現在の『豆まき』で、江戸時代に庶民の間に広がったとか。
なぜ鬼に豆を投げるの?
鬼は邪気や災いの象徴として、形の見えない災害や病、飢饉など、恐ろしい出来事はすべて鬼の仕業だと考えられてきました。
鬼を追い払うための豆は、五穀のなかでも穀霊が宿るとされる大豆。
大豆は昔からお米の次に神事に用いられてきました。
豆は『魔目(まめ)』、その豆を煎ることで『魔の目を射る』ことに通じたため、煎った大豆を鬼の目に投げつけて『魔滅』し、一年の無病息災を祈願する意味合いがあるようです。
鬼に豆を投げつけるのは、鬼を追い払ってみんなの健康を願うためですね(*’▽’)
豆まきの豆の種類
豆まきに使う豆は、煎った大豆か落花生(ピーナッツ)のどちらか。
地域によって異なるようです。
関東から西側は大豆で、東北や北海道は落花生だそう。
煎った大豆を使うのは、前述したように『魔の目(まめ)を煎る(射る)』といった意味合いからと、大豆から芽が出ないようにするためだとか。
芽が出てしまうと魔の芽が出てきてしまい、縁起が悪いと考えられるからだそうです(‘ω’)ヨ
豆まきのやり方は?
豆まきの豆は地域によって異なりますが、前述のように煎った豆か落花生を用意しましょう。
煎った大豆は『福豆』と言います。
鬼は真夜中にやってくると言われているので、豆まきは夜に行います。
家族全員が揃ってから豆まきを開始するといいですね。
本来豆まきは家の主が行うものとされていたり、年男や年女、厄年の人が行う決まりがあったりするようです。
しかし現在は家族で楽しむ行事となっていたりするので、みんなで豆まきをしてもいいですね。
『鬼は外!福は内!』と掛け声をかけてやります。
玄関や窓を開けて『鬼は外!』と言いながら外に向かって豆まきをし、その後鬼が戻らないようにすぐに玄関や窓をしめます。さらに家の中には『福は内!』と言いながら豆まきをします。
一番奥の部屋から鬼を追い出していくように豆まきを行い、最後に玄関に巻いておしまいです。
豆まきが終わったら、1年の厄除けを願ってみんなで豆を食べましょう。
自分の年齢よりひとつ多い数の豆を食べます。(=数え年の考え)
なお、豆まきの仕方や豆の食べ方は地域によって変わるものもあるため、その習慣に倣って行ってくださいね(*’▽’)
また、豆まきが終わったらきちんとみんなでお掃除しましょう。
節分に行われる行事~恵方巻(えほうまき)は必要なの?
なぜ節分に太巻きを食べるのか。
わたしが子どものころにはなかった行事なので分からなかったのですが。
(↑どうせどこかのコンビニの商戦だろうなと思っていました)
どうやら恵方巻が全国的に広まったのは、大手コンビニエンスストアのセブンーイレブンが火付け役となってのことだそうですね。
もともとは、大阪で節分に行われていた太巻き寿司を食べる習慣だったようです。
今や節分と言えば恵方巻の流れとなっていますが、神事的な意味合いはなさそうですね。
恵方巻(えほうまき)とは
節分の夜に恵方に向かって願い事を思い浮かべながら丸かぶり(丸かじり)し、無言で食べ切ると縁起が良いとされている太巻き寿司です。
セブン-イレブンが『大阪には節分に太巻き寿司を食べる習慣がある』と聞いて仕掛けたのが始まりらしく、1989年に『恵方巻』という名称で売り出し、1998年から全国へ広がり、2000年以降に急速に広がって行ったもののようです。
恵方巻の起源は諸説あるようですが、古くの鮨業界広告チラシに史実のように書かれているが信憑性が定かではないものばかりだそう。
・大阪・船場で商売繁盛、無病息災、家内円満を願ったものという説
・船場の旦那衆が節分の日に遊女に巻きずしを丸かぶりさせて遊んでいたという説
・戦国武将が節分の日に丸かぶりして出陣したら戦に勝ったという説
などなど。
太巻きを売り出すときに切り分ける手間を省いた説も。
そもそも、恵方とはなにか。2019年の恵方は?
恵方とは、『その年の良い方角』のことです。
元々はお正月に来臨される歳神様される方角の意味でしたが、現在の『恵方』は陰陽道でその年の干支にもとづき、福の神『歳徳神(としとくじん)』がおられる方角を言います。
歳徳神がおられる方位『恵方』を選んで物事を行えば『万事に吉』とされます。
歳神様や歳徳神については下記でも少し触れています。
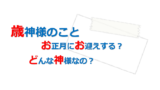
2019年の恵方は東北東だそうです(*’ω’*)ヨ
恵方巻は必要か否かは自分次第
触れました通り、恵方巻には神事的な意味合いはなさそうです。
わたし個人的には、節分の日は太巻き寿司を買ってきて夜の食卓にあげると子どもたちが喜ぶので、節分の日の夕飯は楽だなぁというくらいのものです(笑)
節分の魔除け~柊鰯(ひいらぎいわし)
柊鰯(ひいらぎいわし)とは、柊(ひいらぎ)の小枝に焼いた鰯(いわし)の頭を刺して作る、魔除けや厄除けとして節分に使われる日本で昔から行われている風習です。なんと古くは平安時代から行われていたものだとか。
鬼は柊の葉の痛いトゲと、鰯の生臭い匂いがとても苦手だとされています。そこで、鰯の頭を焼いて匂いを強くしたものを柊の枝に刺し、それを玄関先に飾って鬼が入ってこられないようにする風習があるそうです。
地域によっては豆がらやトベラを添えるところもありますが、昔から匂いの強いものや音の出るもの、トゲのあるものは魔除けや厄除けの効果があると言われてきたからです。
西日本では、やいかがし(焼嗅)、やっかがし、やいくさし、やきさしとも言うそう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
一口に『節分』と言っても、調べてみると昔ながらの風習が見えて面白いものです。
豆まきは今や幼稚園や保育園での園行事としても親しまれていますが、本来の意味を知りながら豆まきをするのも、子どもたちにとっても意味のあるものになるような気がします。
鬼を追い出すための豆まき。
その豆の意味。
健康で幸福な1年を過ごせますように。
そんな願いを込めて。

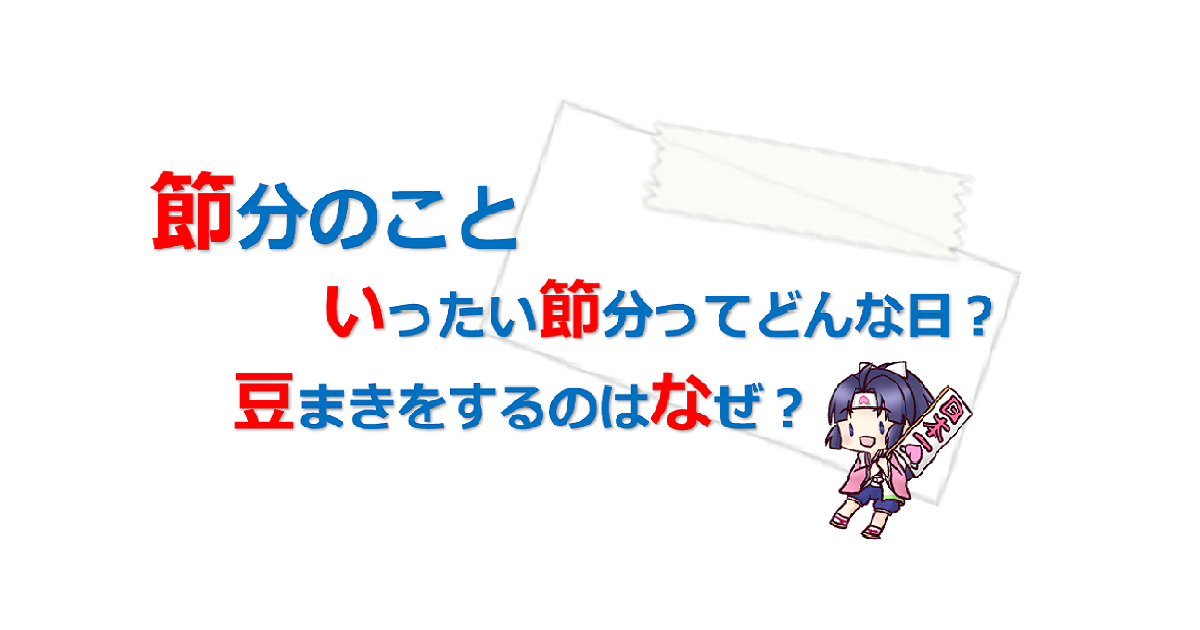


コメント